人生拓く
念願の屋久島縄文杉ツアーに参加してきました
雨に濡れながら、10時間以上も歩いた経験(途中から激しい雷雨)、私は初めてでした
でも、
「行きたいと思った時に、行く。体験してみる」
そんなことを学んだ、貴重な旅でもありました

小学校の時、椋鳩十さんの片耳の大シカを読んで以来、いつかは・・・と、どうしても行きたかった縄文杉でした
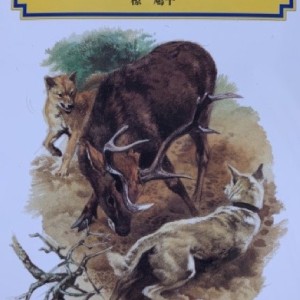
歩行時間 11時間前後 (3時間トロッコ道、2時間半山道)
歩行距離 22km以上
標高差 約700m
総歩数 約40000歩
この行程が、「富士山よりきつい」と聞いてた上に、さらに予報は雨・・・
『ひと月に35日雨が降る』
小説『浮雲』 林芙美子の名言。
屋久島は、8千〜1万mmの雨が降る。世界でも屈指の雨量の島。
そしてまあるいの島の中央部分は、九州で高い山ランキング、1〜7位の1800m級の山々。
ふもとの亜熱帯から山頂には雪が降るという、独特な自然となっているとガイドさんから説明になるほど〜と
~~ 雨対策の事前準備 ~~強力な撥水スプレーをかけ~~~
・レインコート ゴアテックスの上下のヤッケに、
・手袋
・帽子
・登山用靴(軽装のスニーカーでは滑ります)
・ザック雨カバー
あとは
・折りたたみ傘(トロッコ道でこれが必須)
・インナー上下 ソックス(着替え用 濡れないように)
・携帯の雨カバー(すぐに出せるように)
・首元に薄手タオル (何度か変えるといい)
・大判ビニル袋
・アプリ「YAMAP」の縄文杉周辺の地図をダウンロード
~~ 通常持ち物~~
・ヘッドライト(早朝出発なので必須)
・お弁当2個 (朝用・昼用)
・おやつ (チョコ ナッツ)
・水 500mm (山中で補充できます)
・スティック (山中は1本、トロッコでは2本使いました)
・携帯のバッテリー
・バス代 1740円 入山料1000円
(登山用のバスに乗り換え、入山するため必要。ただし12月〜2月オフシーズンはなし。そのままガイドさんの迎えの車で登山口へ)
・携帯トイレ (トイレが途中あるので必要なしだが、心の安心材で1個持参)
<前日 雨>

島に着くと、すぐガイドツアーの支払いと、持ち物の最終確認をします。
持参する弁当は前日19時まで 宿で予約を済ませる(お弁当代700円2個 朝昼分)
<当日 雨>
4時30分: 弁当をホテルで受け取る。ツアーの迎えに来てもらう
5時15分: 登山口へ移動 朝食お弁当食べ、着替え(雨の準備をする)

今回のメンバーは4人。それぞれ単身参加、同世代の男性2人と、70歳女性でした。

登山口に先にいた別の3人組は 「私たちは年だし、明日も時間がまだあるから、弁当を食べてこのまま帰ります」と下山。
5時45分 : 「荒川登山口」を出発
私たちは真っ暗闇の中、黙々とスタート
片道11kmのうち、8.5kmがトロッコ道。歩きやすいが単調な道のため、長く感じる約3時間です。

特に雨の日は、この時間を、濡れずに体力を温存するのが大事だと聞いていました
そこで私は、レインコートの上に、大きなビニル袋を巻き、傘をさして挑みました。
単調な道なので、頭の中では歌いながら、リズムをとって足を進めました
いくつもの橋を渡りますが、手すりの無い橋も3つほど抜けます。ゴ~~ッと言う川の流れの音が暗闇の中で響き、橋を渡るのが怖かったです。
6時25分:「小杉谷集落跡」 最初の休憩ポイントは、小杉谷橋を渡ってすぐ。(トイレなし)
ここは小学校あと地。ここを通るとき、ガイドさんの厳しい表情が・・道を進める中で、後から話をきき、その意味がわかってきました
江戸時代に何本か年貢を納めなかやいけないために数本切った屋久杉も、昭和の時代にチェーンソーでハゲ山になった悲しい話があるそうです
ずっと貧しかった島もその時ばかりは裕福になり、この山の中に早く電気も通ったとか・・・ 昭和42年、伐採の終了とともに一気に人がいなくなった

ここから
「三代杉」が見えてきます。
江戸時代に切った木(親)の上に、子の杉、孫の杉が生えたもの
「仁王杉」が見えます。

8時35分:「大株歩道入り口」標高930mに
トロッコ道終了 中継地点に到着。ここから険しい山道を2時間半
「ここで、もう私は待ちます」 と、もうひとりの女性が断念されます。
「私、退職して、やってみたかったことをひとつずつしてるけど、やはりこんな道はきつい。今更だけど、ずっと仕事ばかりしてきて・・・本当に後悔だわ。
やりたいことは、もっとあなたぐらいの時から始めればよかった」
約2.5kmが不安定な足場の山道が、足元が濡れているので気が抜けません。
木できた階段状のところもありますが、木の根っこむき出しもあり、また川を飛び石のように渡る部分もあります
「翁杉(おきなすぎ)」
2010年に老衰で折れてしまった樹齢2600年。航海の安全を守る神「塩土翁」からその名を拝領した“翁杉”
まさか自分が生きているうちにこうなるとは思わなかったとガイドさん。縄文杉の次に大きなすぎだったそうです

「ウィルソン株」へ
豊臣秀吉の命により大坂城築城(京都の方広寺建立)の為に伐採された杉の切り株。推定樹齢3000年
中心部の柔らかい部分が朽ちて出来た、大人が50人入るという空洞には清水が湧き出し、木魂神社の祭られる祠
(この寺は地震と火災でこの木も消失したそうです)
切り口付近の周囲が13.8m 大正時代に調査・紹介したアメリカの植物学者ウィルソン博士の名を持つ

撮影するポイントは入って右側に座り込んで撮ること
ポイントで撮らないとハートにならず・・・

雨の中、やっと、ハートが撮れた時にはニッコリ

「大王杉(だいおうすぎ)」を過ぎると

やっと世界自然遺産登録地域に

山の神の信仰があった、昔からの住民が守ってきた神々が住む屋久杉。ガイドさんの言葉が胸に響きました
このあたりからは雨もかなりひどくなり、5時間も中腹で、一人待っている女性も心細いだろうと、雨の中のみんな急ぎ足です
「夫婦杉(めおとすぎ)」
雨の冷たさで、時間もうろ覚えです 自分で写真を撮る余裕がなくなり、ガイドさんがみんなをポイントで撮ってくださったのだけに

11時 やっと、「縄文杉」に到着!! さらに雨がひどくなってきました

この展望デッキ、3年前まではもっと上の方にあったそうです。
ただ縄文杉が弱ってきていて、ひょっとして何かあれば危険と、数メートル下がったところになったそうです。


山頂に着く頃には雷もなり始め、長居は体が冷えてくる
お弁当を駆け込み食べて、また急ぎ戻ることに
11時25 下山 スタート
戻り始めるとますます雨はひどくなり、雷と風、雨は下から振ってくるような気さえする状況に。もう雨対策なんて状況でもなく、
山道が雨水流れ、ずぶ濡れになっていきました

屋久島のシンボルである縄文杉を見た後は来た道をひたすら戻りました。
横の川が濁流となっています
足元滑り落ちないように細心の注意を払って、進みます。
川を何箇所か横切るのですが、短時間に行きと様子が違っています。
沢下りの形相さえしました
12時50:中継ポイントに戻った時にはずぶ濡れです
13時: 全員で出発


14時50:トイレ休憩
15時45: 小杉谷集落跡 休憩ポイントまで戻り、ガイドさんがお湯を沸かしてくださりコーヒータイムを。行きた心地がやっとしてきました
16時10:荒川登山口 到着
17時 ホテルへ
雨対策、寒さ対策は必須と言われる山の諸先輩がたの話が本当に身にしみました。
一歩間違うと・・・気を抜くと、落ちる箇所はなんども出てきました
「自分が知ってるだけでもドクターヘリが今年3回飛んだ」と淡々と話すガイドさん
あの雷雨の中、自分たちだけなら、まず経験しなかった今回の登山。
結局、この日登ったのは私らだけ・・・ こんなことができたのは、時に厳しく、そしてさりげなく様々、配慮されてるベテランガイド 坂上さんのおかげで無事に帰ることができました
ガイドさん曰く(息子にも聞いたことあり)、山には山の神がいて、特に屋久島は神々が集まる日が年に3回は山の日があるそうで、「その日は人は山に入らないこと」
太古の昔から、大切にしてきた事を観光ならなんでもいいという事はないと話してらっしゃいました。
本当にありがとうございました
そしてグランチア世代の女性の言葉が響きました
行きたいと思った時に、行く。体験してみる
そんなことを学んだ旅でもありました

翌朝は、こんなに快晴。

大川の滝をみて、昨日の雨が流れてきてるかな〜と思い出しました。
午後には仕事に戻り、夜はレッスン。(直行便があるのと、空港がどちらも便利なので、2時間後には仕事に戻ると言うこともできるんですね・・)

これまた、楽しい時間でした このキャンプはまた別にまとめようと思います
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
ちなみに九州の山、標高上位100山
1 宮之浦岳 みやのうらだけ1936m 屋久町・上屋久町
2 永田岳 ながただけ 1886m 上屋久町
3 栗生岳 くりおたけ 1867m 上屋久町・屋久町
4 翁岳 おきなだけ 1860m 上屋久町・屋久町
5 安房岳 あんぼうだけ 1847m 上屋久町・屋久町
6 黒味岳 くろみだけ 1831m 上屋久町・屋久町
7 投石岳 なげしだけ 1830m 上屋久町・屋久町